薬に頼らない薬剤師ゆみぽが伝える 心と身体が笑顔になる栄養学 |
第8回「肝をケアする薬膳の考え方」
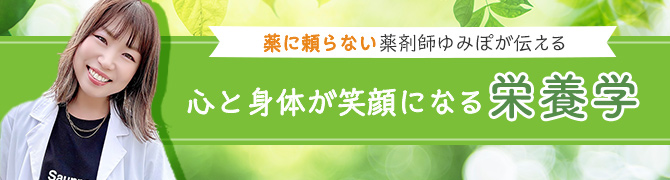
みなさんこんにちは!
薬に頼らない薬剤師のゆみぽです。
薬膳において、「肝」は中医学(東洋医学)の重要な臓腑の一つであり、血の貯蔵と流れの調整、情緒の安定、解毒の役割を担います。
今回は肝機能を改善し、健康を維持するための薬膳的なアプローチについて詳しく説明します。
肝をケアする基本的な薬膳の考え方
(1) 肝の主要な働き
- 気血を巡らせる
肝は全身の「気」(生命エネルギー)と「血」の流れをコントロールします。
- 情緒を安定させる
肝が不調になると、イライラやストレスが増えるとされます。
- 解毒と体内の調整
現代的な観点では、肝臓は毒素の代謝と解毒を行う臓器に例えられます。
(2) 肝の状態に影響する要因
- ストレスや感情の乱れ(肝気鬱結と呼ばれる)
- 食生活の不摂生(脂っこい食べ物やアルコールの過剰摂取)
- 睡眠不足
肝をケアするための薬膳では、「養肝」「疏肝」「清肝」という方法を使います。
肝機能を改善する食材
薬膳で用いる食材には、「肝」をサポートする特性を持つものがいくつかあります。
(1) 養肝(ようかん):肝を滋養する食材
- 緑色の野菜:中医学では「緑」は肝を助ける色とされています。
例:ほうれん草、春菊、小松菜、ブロッコリー
- 酸味のある果物:肝を保護する作用があるとされています。
例:レモン、梅、柑橘類
- 血を補う食材:肝は血を貯蔵するので、血を補うことが肝の健康に重要。
例:黒ごま、クコの実、なつめ、鶏レバー
(2) 疏肝(そかん):肝の詰まりを解消する食材
ストレスや疲れで「気」の流れが滞ると、肝がダメージを受けます。気の流れを促進させるには以下が効果的です。
- リラックス作用のあるハーブや食材:菊花茶(菊の花茶)、ミント、百合根、柑橘系の皮(陳皮など)
(3) 清肝(せいかん):肝の熱を冷ます食材
肝に「熱」がこもると、不眠やイライラ、顔のほてりなどの症状が出やすくなります。
- 冷性の食材:キュウリ、ゴーヤ、トマト、セロリ
- 解毒作用のある食材:緑豆(緑豆スープ)、ハトムギ、山査子(さんざし)
薬膳スープや簡単なレシピ
以下のレシピは、肝機能の改善に役立ちます。
(1) クコの実と鶏肉のスープ
- 材料
鶏肉(ささみや手羽先) 200g、クコの実 大さじ1、なつめ 2~3個、生姜スライス 少々
- 作り方
1.鶏肉を下茹でし、臭みを取る。
2.水と材料を鍋に入れ、弱火で30分~1時間煮込む。
3.塩少々で味を調える。
(2) 緑豆スープ
- 材料:緑豆 100g、水 1リットル、砂糖またはハチミツ(甘さ調整)
- 作り方
1.緑豆を洗い、水に浸けておく(30分程度)。
2.水を入れた鍋に緑豆を入れ、柔らかくなるまで煮込む。
3.甘味を加えて温かいまま、または冷やして食べる。
生活習慣のアドバイス
薬膳は食事だけでなく、全体的な生活習慣の見直しも大切です。
- 早寝早起き:特に夜11時~3時は肝の修復時間とされ、睡眠が重要。
- ストレス管理:深呼吸や瞑想、散歩を取り入れる。
- 軽い運動:気血を巡らせるため、ヨガや太極拳がおすすめ。
注意点
- 体質に合わせる
個人の体質(冷え性、虚弱体質など)によって適切な食材や調理法が異なります。
- 過剰な摂取は避ける
特に冷性食材は取りすぎると逆効果になることがあります。
- 専門家に相談する
持病や薬を服用中の場合は中医学の専門家や医師に相談してください。
日々の食生活とストレス管理を意識することで、肝機能を薬膳的にサポートできます。健康的な体づくりを目指してください!
Instagramでの情報発信を精力的に行ってます。

また食生活のアドバイスを行う個別カウンセリングも行っております。
ぜひ、遊びに来てくださいね♩
Instagram:@yumipo.a


