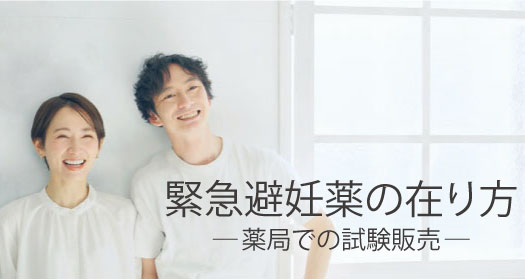地域に根ざす企業のDX戦略 ―事業の多様化と組織力強化、その鍵を握る本部機能とは―

取締役 統括本部長 兼 ヘルシーフード事業部長 西村 翼 様
コンサルティングファームや銀行で、IT導入やM&A、企業金融に幅広く従事。
その後はマネジメントコンサルタントとして、業務改善や再生支援、M&Aアドバイザリーを経営層に提供。
現在は共和メディカルの統括本部長として、財務・人事・新規事業を統括し、DX支援にも注力。
共和メディカルグループ
1978年設立。大阪府東大阪市に本社を置き、ジェネリック医薬品の卸販売をはじめ、調剤薬局の運営、訪問看護・リハビリテーション、ヘルシーフードの製造・販売、医療機関の開業支援、海外での薬局展開など多岐にわたる事業を展開。
今回は、こうした多角的な事業展開の背景や、それを支える統括本部の業務改革、さらにDX学校を通じた中小企業支援の取り組みについて、西村部長にお話を伺いました。
―まず、御社の事業内容について教えてください。
もともとはジェネリック医薬品の製造を手がける共和薬品工業株式会社の販売会社としてスタートしました。現在は、大阪・和歌山で医薬品卸業を展開するとともに、調剤薬局を11店舗運営しています。さらに、当社の特徴として、「へルシーフード事業」と「訪問看護・居宅介護支援・リハビリ事業」など、医療・健康を軸とした多角的な事業展開を行っています。
― さまざまな取り組みをされているとのことですが、事業に込められた想いや特徴についてお聞かせください。
「ヘルシーフード事業」では3店舗の飲食店を経営しています。そのひとつ、大阪・上本町の日赤病院の隣にある「patisserie natura(パティスリーナトゥーラ)」では、糖質制限やグルテンフリーに対応したスイーツの開発・販売を行っています。

〒543-0027
大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-38 ロイヤルパークス桃坂 1F
☎06-4305-2277
営業時間:11:00-19:00 ※売り切れ次第、営業終了
定休日:木曜日・日曜日
また、吹田市の医療・福祉複合施設内にある「日本のいいもの食堂 ハレとケ」では、サービス付き高齢者住宅の食堂を受託し、一般の方にもご利用いただける”地域に開かれた食堂”として運営しています。「食を通じて健康を届ける」ことを重視して、地域の皆様の健康づくりに貢献するという視点で取り組んでいます。

〒565-0862
大阪府吹田市津雲台5-11-1-3 パークナードフィット津雲台 1F
☎:06-6155-6005
営業時間:11:00-15:45
「訪問看護・居宅介護支援・リハビリ事業」は、訪問看護ステーション3ヵ所とケアプランセンター1ヵ所を拠点として展開しています。その中の一つ、吹田市津雲台にある訪問看護ステーションでは、一般住宅の集会所の活用策として「みんなの保健室」を受託運営しています。
時にはご高齢者の方が健康相談に来られたり、子どもたちが宿題をしに来たり、家族の帰りを待つ居場所になったりと、看護師が常駐する開かれたスペースとして地域に溶け込むような活動をしています。
こうした取り組みから、輪が徐々に広がっています。
こうした事業展開の根底には、企業スローガンである「地域医療に貢献し、健康を通して社会に奉仕する」という理念があります。私たちは、医療・食・地域の連携を通じて、この理念を具体化しています。

― 西村さんが部長を務める統括本部では、どのような業務を担っていますか?
私たち統括本部は、いわゆるバックオフィス部門─人事・総務・経理─を担っています。加えて、広報、新規事業の推進、業務改革も担当し、単なる裏方ではなく“攻め”の機能も持っていることが特徴です。社内外への情報発信、そして社内の仕組みそのものを変えていくような業務にも積極的に取り組んでいます。
― 社内報も拝見しましたが、こちらも統括本部で制作されているのですよね。
はい、そうです。年に2回の社内報を通じて薬剤師の海外研修の様子や営業部の成果発表、薬局スタッフの学会報告、健康イベントの紹介など、部署の枠を超えた取り組みを全社員で共有しています。互いに刺激を与え合い、社内の一体感や前向きな雰囲気づくりに貢献しています。

― 現在、その体制は何名で運営されているのでしょうか?
私を含めて4名体制です。少数で、人事・総務・経理・広報・新規事業すべてを担っています。効率化のために、業務の見直し・改革を徹底してきました。
― 具体的にはどのような改善をされたのですか?
まず、会計・給与・勤怠などのソフトをすべて連携可能なクラウドシステムに統一しました。よく「CSV連携が可能なシステム」として販売されることが多いですが、実際には手間がかかったりするため、一気通貫、ボタン一つで連携できることを優先させて同じシリーズで業務を回すように見直しました。
結果として、以前は給与計算に3営業日かかっていた作業が、今は私1人で2〜2.5時間程度で終わります。
― 統括本部長に就任された当初は、どのような課題がありましたか?
私が入社した当時は、属人的で、引き継ぎが困難でした。ベテラン社員が辞めると業務が回らなくなる状況でしたので、業務の標準化を図り、ツールや外部サービスを活用して、誰でも同じように処理できる体制を作りました。
― 改革によって得られた成果はありますか?
大きなところで言うと、「人を増やさなくても、新しいことにチャレンジできる余白が生まれた」ことです。削減できた時間を、新規事業や新しい取り組みに振り向けられるようになりました。
― 西村さんはコンサルティング事業部としても活動されているとのことですがどのような活動をされていますか。
2021年に「コンサルティング事業部」を新設しました。コンサルティング事業部では、医薬品卸事業で築いた約1,500の取引先との関係性を活かし、経営支援を行っています。内容は、DX推進やM&A支援、管理栄養士を活用した薬局支援など多岐にわたり、実践的な課題解決に取り組んでいます。
― その中の業務の一環として、DX学校を始められたと伺いました。
その背景にはどのような想いがあったのでしょうか?
私自身、実際にデジタルツールを導入したことで業務がとても楽になったという実感がありました。当社のお客様には、家族経営で小規模な昔ながらのやり方を守り、デジタルに苦手意識を持たれている方も多く、なにかお手伝いできることがあるのではないかと感じていました。
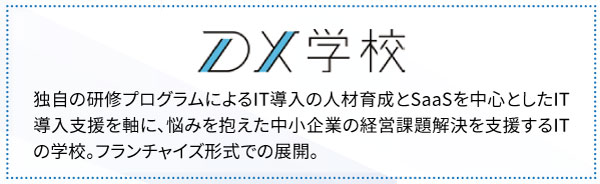
―「 DX学校」の内容や学びのスタイルについて、どのような点に魅力を感じられましたか?
教材を提供して終わりではない、「魚を与えるのではなく、釣り方を教える」という考え方です。単なる座学ではなく、現場に活かせる実践的な内容になっている点が魅力だと感じています。
たとえば、経営者の方が受講された場合は、最終的に「自社の課題と改善提案」をまとめるところまで取り組んでもらいます。社員の方であれば、それを経営者に向けてプレゼンテーションする。学んだことをきちんとアウトプットし、実務に反映させるプロセスが組み込まれています。
― DXの重要性は広く叫ばれていますが、現場とのギャップも大きいと感じますか?
まさにそうですね。
医療DXという言葉だけが先行していて、「何から手をつけていいのかわからない」という現場の声は本当に多いです。だからこそ、そのギャップを埋める存在が必要だと感じています。医療DXは厚生労働省が旗振りをしていることもあって、例えばオンライン資格確認や調剤機器のデジタル化などは、補助金も出ていますし、ある程度は進んできていると思います。ところが、現場で最先端の機器を使っていても、バックオフィスに目を向けると、紙のタイムカードを使い、夜遅くまでエクセルで給与計算しているといった状況も少なくありません。
現場だけでなく、経営や運営全体を見渡したときに、“昭和的なやり方”がまだ根強く、そこにギャップを感じます。現場だけでなく、会社運営全体の効率化が必要だと思っています。だからこそ、DX学校としては、業務全体に対してDX導入を支援していくことが大きな役割だと思っています。
― バックオフィス全体のシステムの導入には時間がかかりそうな印象ですが、実際はどのくらいの期間がかかりましたか?
当社では、会計システムの入れ替えに約3ヶ月です。どこかで“やるぞ”と決めて動かないと、ズルズル先延ばしになります。10店舗以下くらいの薬局であれば、3ヶ月もあれば対応可能です。運用に慣れるまでには半年ほどかかるかもしれませんが、スタートラインには十分立てます。
― 費用面の負担はどうでしょうか?
昔みたいに、自社専用にシステムを作って……という時代と比べれば、かなりハードルは下がっています。
今は1人あたり月額数千円で始められますし、気に入らなければすぐにやめられます。昔は数百万かけて専用システムを作り、サーバーを社内に置いて、停電対策までして…という手法でしたが、今はGoogleやMicrosoftのクラウドを使えば、高度なセキュリティを確保することができます。
何千億円を投じてセキュリティを守っている企業のサービスを使えるのだから、コスト面でも安全性の面でも、クラウド型の方が断然有利ですね。
― 最後に、DXに悩んでいる医療関係の方に向けてメッセージがあればお願いします。
「うちは関係ない」という中小企業さんも多いですが、本当にDXの恩恵を一番受けるのは中小企業だと思います。悩んだら、まずやってみたらいいと思います。昔と違って、導入コストもリスクも下がっています。
特に薬局業界は、アナログ業務がまだまだ多いです。大手は専用のシステム部門を持っていて、最新のシステムを入れて効率化しています。
そこに対抗するには、中小企業も積極的にデジタル化していかないと、従業員が疲弊してしまいます。
厚生労働省も「対人業務の強化」を求めていて、それを実現するにはツールの力が必要です。補助金なども活用して、少しずつでも取り組んでいくことが、薬局の未来のためにも重要だと思います。

●お問い合わせ●
HP:https://dx-school-osakakita.jp/
電話:06-6224-6224(共和メディカル代表)