薬に頼らない薬剤師ゆみぽが伝える 心と身体が笑顔になる栄養学 |
第14回「麦茶の薬膳的メリットとは?」
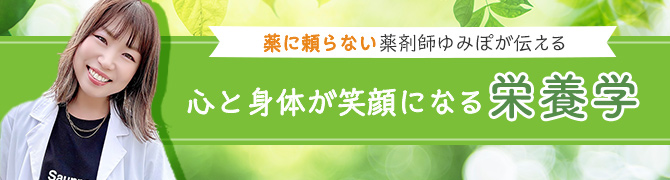
みなさんこんにちは!薬に頼らない薬剤師のゆみぽです。
まだまだ残暑が残っていますがいかがお過ごしでしょうか?
今回は今の時期にもぴったりな麦茶のご紹介です!
麦茶は日本の夏に欠かせない飲み物ですが、薬膳の観点から見ても非常に優れた効能を持っています。
薬膳では、食材や飲み物を「体質を整えるもの」「季節に合ったもの」として考えるため、麦茶の役割を理解すると日々の養生に役立ちます。

まず、麦茶の原料である大麦は「涼性」の性質を持ち、体内の熱を鎮める働きがあるとされます。
夏は暑さで
「心火(しんか:心臓にこもる熱)」
「暑湿(しょしつ:蒸し暑さによるだるさ)」
が生じやすく、倦怠感や食欲不振を招きます。
麦茶を飲むことで熱を和らげ、体をすっきりと整えてくれるのです。
特に熱中症予防や、火照りやすい体質の方にはぴったりといえます。
さらに、大麦には胃腸の働きを助ける作用があります。
薬膳では「健脾(けんぴ)」といって、脾胃=消化器系を整えることが健康の基本とされます。
麦茶は冷やしすぎず、ほどよく胃にやさしいため、油っぽい食事や甘いものを摂りすぎて胃が重いときにも適しています。
冷たい水やジュースに比べて胃腸を傷めにくいのが特徴です。
また、麦茶には「利水作用」があるとされます。
これは体内にたまった余分な水分を排出し、むくみを改善する働きのこと。
湿気の多い日本の梅雨から夏にかけて、体がだるくなったり足がむくんだりするのを和らげる助けになります。
特にデスクワークや立ち仕事で足が重い方には日常的なサポートとなります。
薬膳的に見てもう一つ大切なのは「無カフェイン」であること。
お茶やコーヒーと違い、麦茶は眠りを妨げず、小さな子どもから高齢者まで安心して飲めます。
薬膳では「陰(いん)を養う=体を潤す」ことも重視しますが、麦茶はのどや胃腸をやさしく潤し、口の渇きを和らげるのに適しています。
授乳中の方や、睡眠を大切にしたい方にとっても安心できる飲み物です。
まとめると、麦茶は薬膳的に
- 体の余分な熱を冷ます
- 胃腸を助ける
- むくみを改善する
- 無カフェインで誰でも安心
といったメリットを持つ、まさに「日本の夏の養生茶」といえるでしょう。
普段の飲み物を麦茶にするだけで、薬膳的な体調管理を自然に取り入れることができます。
ぜひ試してみてくださいね!
Instagramでの情報発信を精力的に行ってます。

食生活のアドバイスを行う個別カウンセリングも行っております。
ぜひ、遊びに来てくださいね♩
Instagram:@yumipo.a


